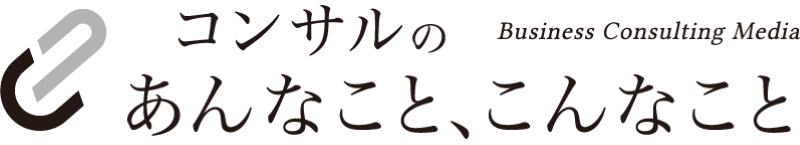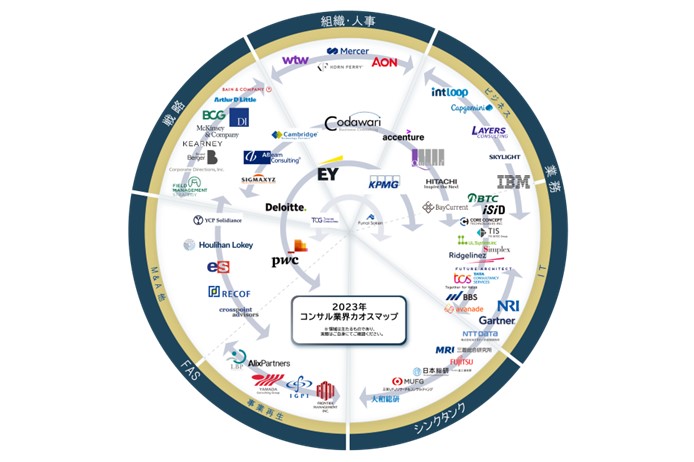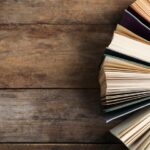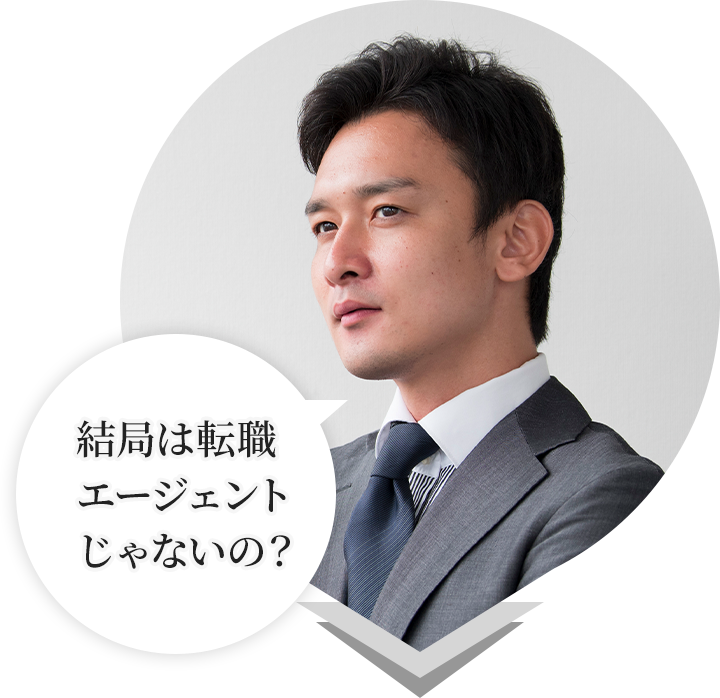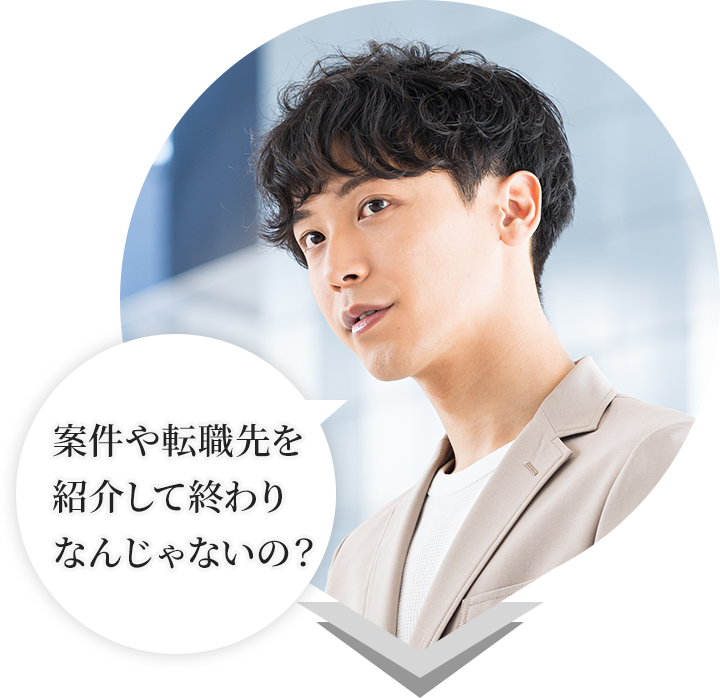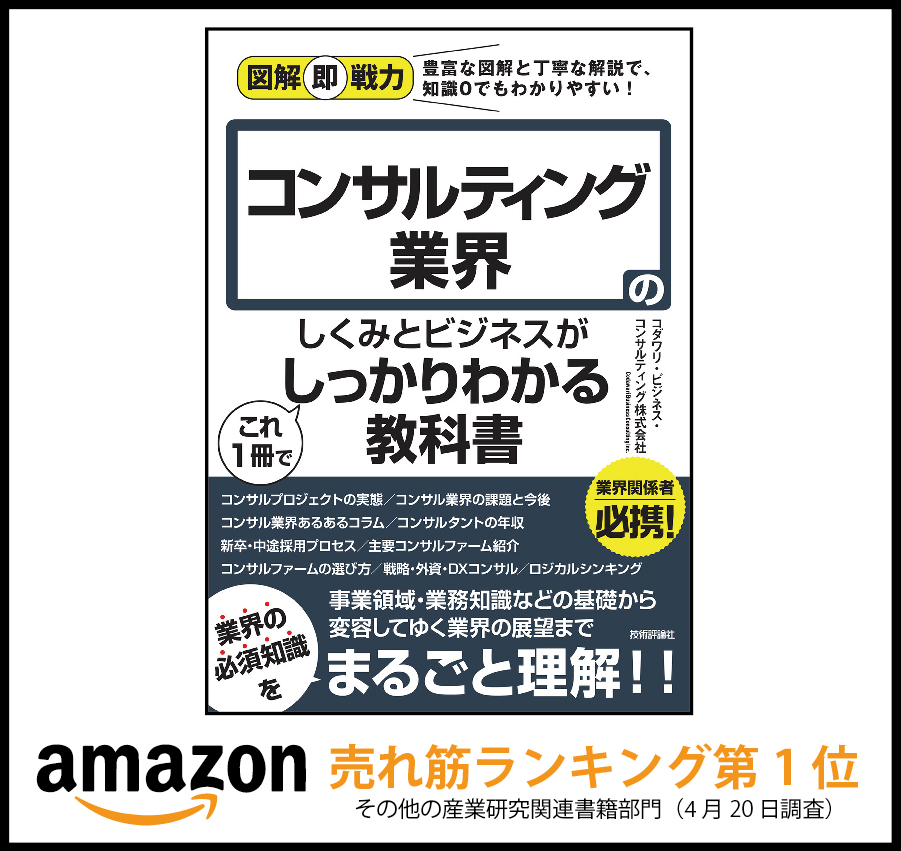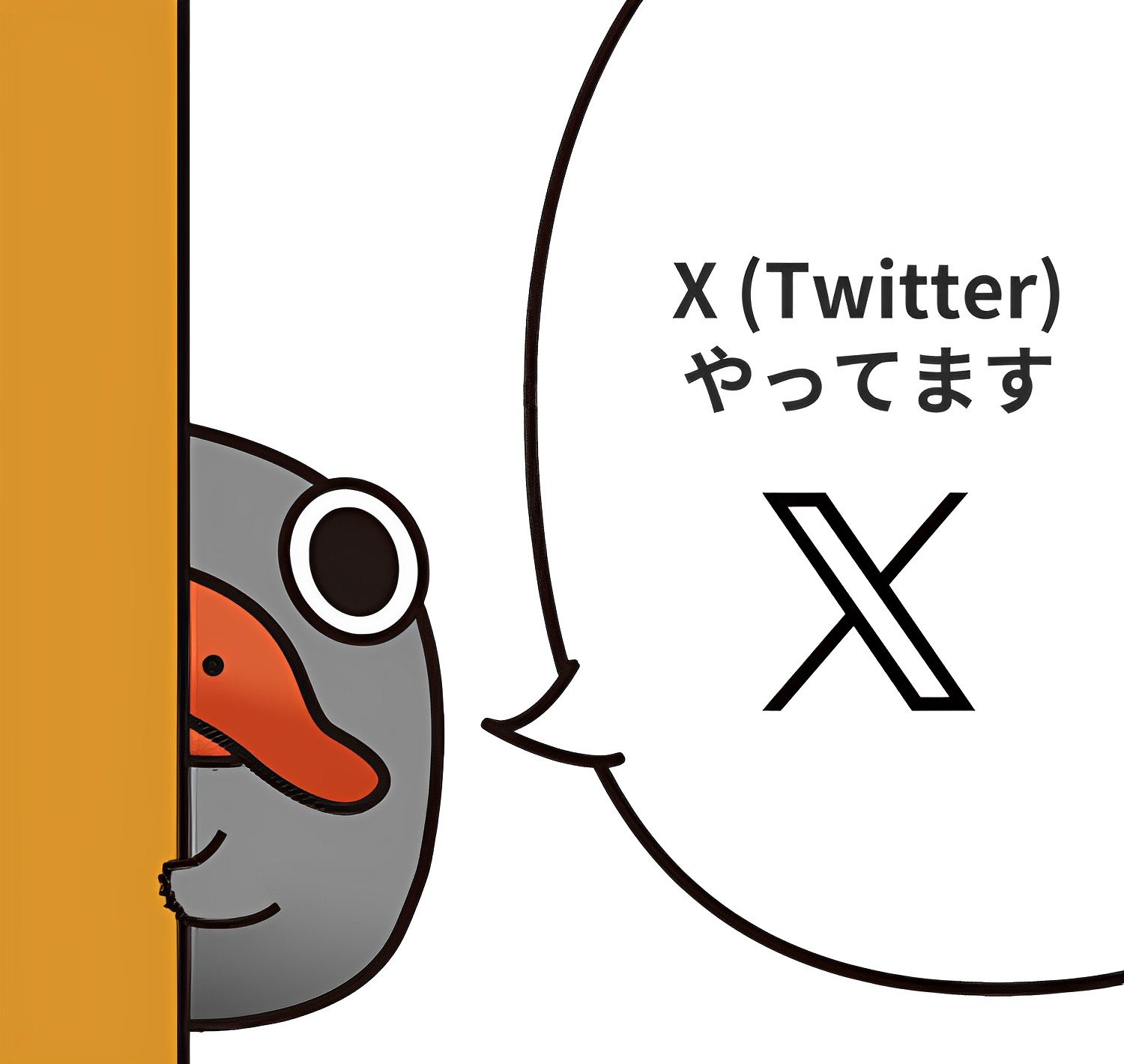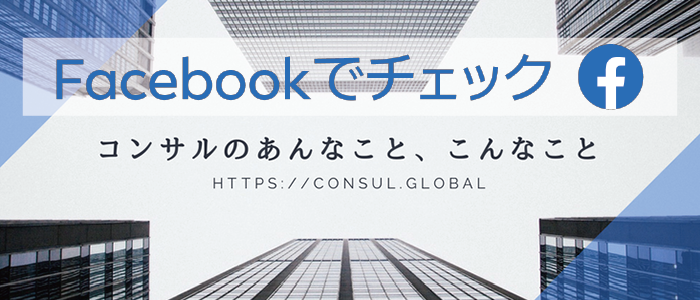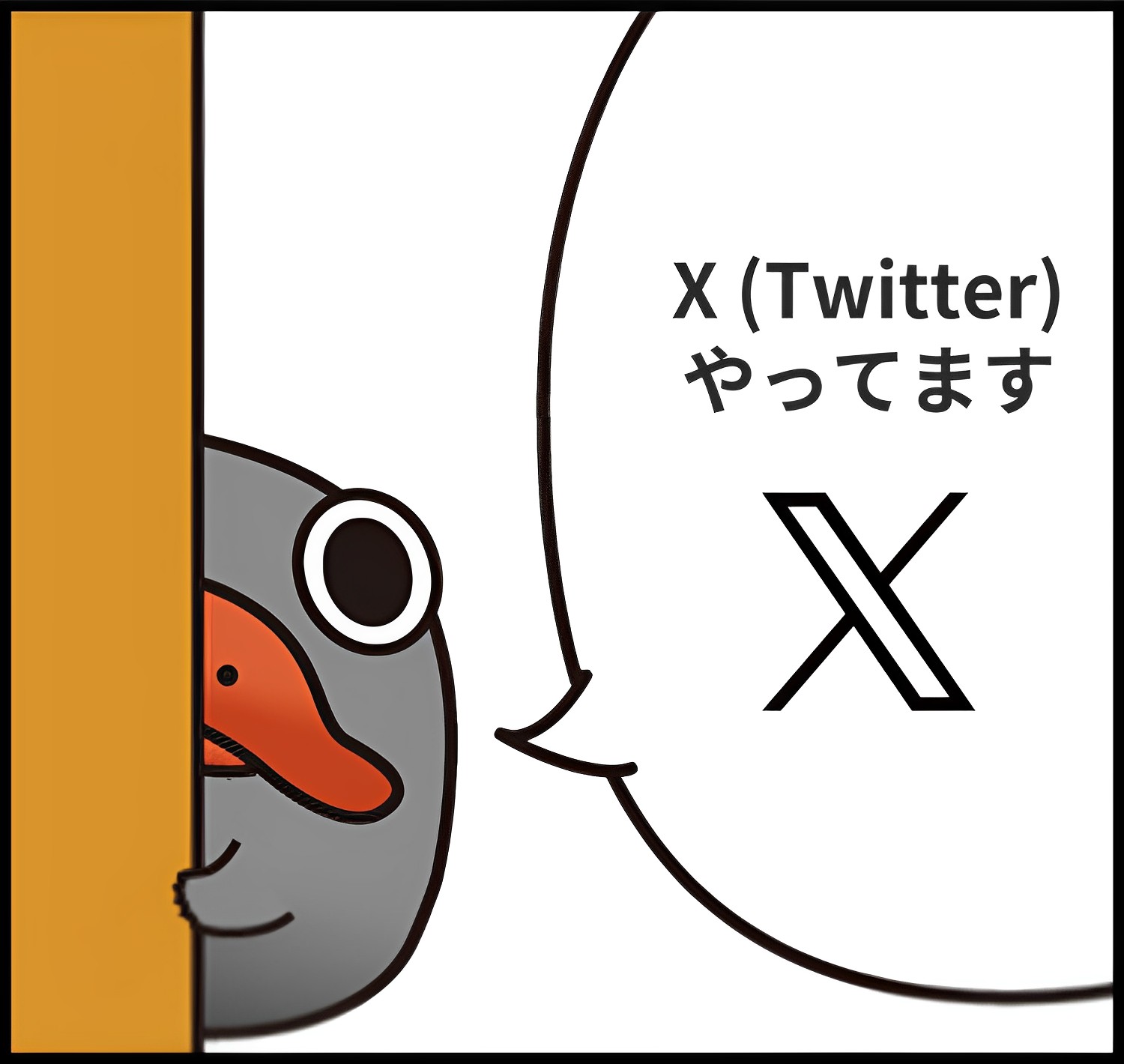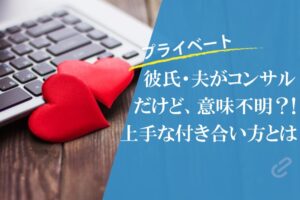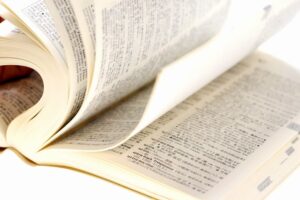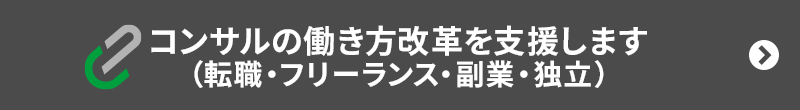view 102629
よく聞くコンサル用語あれこれ|「アベる」 「KT」「MECE」 「ロジ周り」 の意味とは?
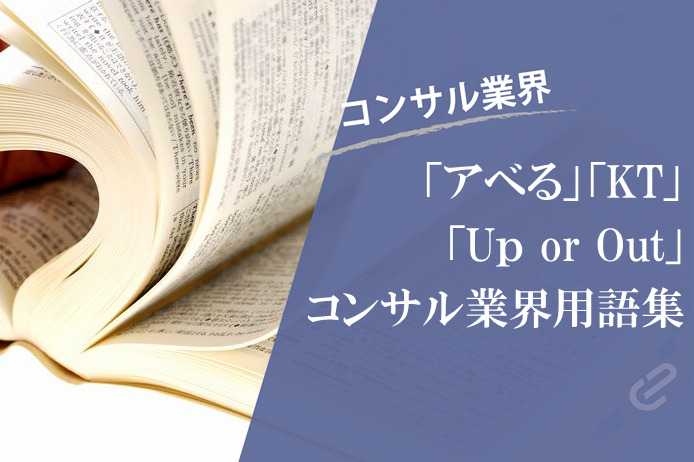
コンサル業界特有の用語24選
コンサル業界でよく聞くフレーズを集めました。今回取り上げる24の用語は、スタッフレベルが上司からよく言われる言葉やプロジェクト参画時によく聞く”あるある”業界用語となります。特に、今春のブランニュー*や、これからコンサル業界に転職してキャリアをスケール*させたい方々は、これらの用語にキャッチアップ*しておくことで、入社直後の戸惑いを減らし、ヘッドスタート*しましょう!
上記の文章はおおげさですが、コンサル業界は非常にカタカナ語やアルファベットが多い業界です。しっかり各ワードの意味をおさえて、認識齟齬がないようにしていきましょう。
*ブランニュー:新卒
*スケールする:(事業規模などが)拡大する
*キャッチアップ:遅れを取り戻して追いつくこと
*ヘッドスタート:先取りしてスムーズな立ち上がりをすること
目次
アベる

忙し過ぎて少しはアベりたいよ。
| ▼意味▼ 「available」の略語である「アベる」。 「アベ」と言ったりもします。プロジェクトにアサインされておらず身体が空いている状態、要するに社内ニート(暇人)ということですね。 |
通常、アベっている期間は、社内業務を担当したりやスキルアップのための学習をしたりして過ごします。でも、コンサルでは稼働率(どれだけプロジェクトに入っているか)がKPIになっていることが多いので、アベる状態が続いていると期末の人事評価に関わるなど、死活問題になることも。
アサイン

より成長したいので、次は難易度の高いプロジェクトへのアサインを希望します。
| ▼意味▼ アサイン(assign)とは「任命する」や「割り当てる」という意味の言葉です。コンサル業界ではプロジェクトにコンサルタントがメンバーとして参加することを指します。 |
プロジェクトへのアサインは、アサイン会議で調整していきます。アサインプランに合わせプロジェクトマネージャーがコンサルタントとアサイン面談を実施。プロジェクト内容や必要スキルを相互に確認してから、プロジェクトへの参画が決まります。
なお、プロジェクトを離れることを「リリース」と言います。リリースは、プロジェクト終了時やフェーズの切り替わりで行われることが大半ですが、プロジェクトやチームとのミスマッチで離れるケースもあります。クライアントからの不評といったネガティブな理由でリリースされた場合、次回のアサインに影響するのは言うまでもありません。
KT

オンラインで構いませんので、来週中にKTをお願いします。
| ▼意味▼ 「Knowledge Transfer」の略語で、要するに引き継ぎのことです。 このほかにも、「ナレトラ」「スキトラ(Skill Transferの略)」という言われ方をすることもありますが、基本的に意味は同じです。 |
コンサル業界は人材の流動性が高いため、プロジェクトの途中でチームメンバのスイッチが行われることがあります。そのため、プロジェクトに関する重要情報は、効率よく引き継がなければなりません。マネージャには、日頃からKTの可能性を踏まえたプロジェクト設計が求められます。
アウトプット

Oさんのアウトプットはいつも質が高いですね。何か秘訣はありますか?
| ▼意味▼ 「output」。元々はコンピュータ用語で、コンピュータに対して「入力」することを「input」、コンピューターから「出力」することを「output」といいます。コンサルでは、自身が作成する資料を指します。 |
「コンサルはアウトプットが全てだから」とよく言われますが、まさにその通りです。アウトプットのみでコンサルとしての資質が判断されるといっても過言ではありません。パワポの作成が下手だと出来の悪いコンサルだと思われるので、パワポなんてお絵かきだなどと侮ることはできません。
カットオーバー(C/O)

このシステムのカットオーバーは来年の9月末です。
| ▼意味▼ 「cut-over」。この言葉はIT業界出身の方には馴染み深いかもしれません。 新しいシステムを利用開始することを指します。コンサルが業界では、システムだけでなく、新規事業や組織変革など、新たな施策を実施する際にも使われれます。 |
ちなみに、英語では”go live”(ゴーライブ)と言うのが正しい表現です。
日本語でも英語でも通じる単語に”launch”(ローンチ)がありますが、「新しいモノやサービス」を対象とするため、バージョンアップ時にも使う「カットオーバー」とはニュアンスが異なります。
シナジー

a社とのM&Aによるシナジーについて、内部向け資料をまとめておいてくれる?
| ▼意味▼ 「共同作業」といった意味があるものの、コンサル的には「相乗効果」といった意味でつかわれることが大半です。「シナジー効果」と言うこともあり、M&Aや経営の多角化を行う際に、それぞれが元々持っていた以上の価値を生み出す効果を指します。他にも、取り組み施策に対してこういった効果もあるという派生的なケースで使ったりもします。 |
「シナジー効果」の反対語として、「アナジー(Anergy)効果」があります。M&Aにおいて、買収先企業の旧経営陣の労働意欲低下や優秀人材の流出などはよく聞く話ですが、これはアナジー効果と言えるでしょう。
コミットメント(コミット)

プロジェクトにコミットメントして、クライアントに評価されたときにやりがいを感じます!
| ▼意味▼ 某CMで「結果にコミットする」というキャッチフレーズを聞き、何となく知っている方も多いのではないでしょうか。コンサルシーンにおいては「約束する」といった意味合いで、責任をもって職務を果たすという強い意志を表す際に使用されます。 |
決意表明的な意味合いも強く、提案書でもこの表現を使ったりします。コンサルプロジェクトでも上司が部下に「コミットメントしていない」とか「コミットメントが全く足りない」と叱咤するシーンがよく見受けられます。
Up or Out

先輩の時代は「Up or Out」が絶対だったのですか?
| ▼意味▼ 直訳すると「昇進するか辞めるか」ですが、意味合い的には「昇進できないものは去れ」となります。 |
他の業界では、出世とは関係なく定年まで地味にこつこつ長く続けることが大事と言われたりもしますが、コンサルは毎年結果を出してなんぼと言われます。
コンサルファームにも昔はあった文化で、戦略や一部ベンチャーにはこの考えは色濃く残っています。大手総合系ファームは、日本で経営する上では労働法は無視できないので、この考えは次第に薄れていっているような気がします。そんな大事な言葉まで、わざわざ英語を使って表現するところもコンサルらしいと言えます。
Mup

Mupの採用を強化していますが、各社同様で全然採用できないです…
| ▼意味▼ Mup(エムアップ)とはマネージャー以上の役職を指します。コンサルの転職市場や採用関連で比較的よく使われます。コンサル同士の会話でもサラっと登場することがあるので、知っておいて損はないでしょう。 |
コンサルプロジェクトは、マネージャーが中心となって推進していきます。そのため、マネージャーという役職は、コンサルタントがまず最初に目標とするタイトルと言えるでしょう。しかし、昨今は労働環境のホワイト化が進み、残業規制のあるメンバレベルには一定以上の作業を依頼できなかったり、期限内に仕上がらないアナリストのタスクをマネージャー自身が巻き取って尻ぬぐいしたり、と「私のワークライフバランスはいずこに」といった状況のエムアップも多いようです。
N2H(nice to have/ナイス トゥ ハブ)

必須にしてしまうと人材が出てこないので、Nice to Haveでいいです。
| ▼意味▼ Nice to have(ナイス トゥ ハブ)とは、「(なくても良いけど)あった方が良い」ことを意味します。 資料やメール・チャットなどではN2Hと表すこともあります。 |
主に人材要件で使われ、必須要件のことはMust to have(マスト トゥ ハブ)と言うことが多いです。コンサル人材の「Nice to Have」「Must to have」には、どのような要件があるのかは、こちらを参考にしてみてください。
インダストリーカット・ソリューションカット

VUCAの時代、インダストリーカット・ソリューションカットされた組織体制だと支援にも限界があります。
| ▼意味▼ 大手総合系コンサルファームでは、「インダストリ(業界)」と「ソリューション(支援領域)」を軸としたマトリクス型の組織編制とすることが大半です。 例えば、「インダストリ=製造、通信、医薬・医療、消費財…」「ソリューション=会計、戦略、M&A、組織人事、サプライチェーン…」というように分類され、コンサルタントはいずれかの部門に所属し、関連プロジェクトに参画しながら専門性を高めていきます。 略して「インソルカット」と言う人もいるほか、「インダストリ」は「セクター」、「ソリューション」は「コンピテンシー」「オファリング」「サービスライン」などと呼ぶ場合もあるようです。 |
対して、「ワンプール制」を敷くファームもあります。コンサルタントはインダストリーやソリューションに縛られず様々なプロジェクトに参画できるため、多角的な視野を持って複数の専門性を磨くことができます。
MECE

昨日作ってもらった比較表だけど、ちゃんと項目がMECEになっているか確認した?
| ▼意味▼ MECE(ミーシー)は「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の略語で、漏れや重複がないことを言います。つまり、必要な要素を完全に網羅しており、尚且つ、それらの要素に重複がないという状態です。 |
コンサルに最も求められるスキルと言っても過言ではないのが、ロジカルシンキングです。
「MECE」はその基本の考え方で、物事やロジックを分解する時に必ずといっていいほど持ち出される概念です。
コンサル1年目の研修でも、「MECE」と「So what/Why so(論拠の組み立て方)」を叩き込まれます。
もし「MECE」などの言葉に聞き覚えがない場合は、一度ロジカルシンキングの考え方を知っておくことをお勧めします。参考書籍はこちらでも解説していますので、チェックしてみてください。
粒度

先ほど依頼された調査ですが、どの程度の粒度で調べればよいでしょうか?
| ▼意味▼ 粒度という言葉は、一般的には「細かさ」を表すことが多いと思いますが、コンサルの現場では、「詳細さ」という意味で使うことが多いです。 |
コンサルとして仕事をする上で、頻繁に聞く言葉で、かつ我々を悩ませる頻度が高いのが「粒度」です。
例えば業務の一環で、ある業界に関する調べ物をする時、どのくらいの粒度で情報が必要なのか(大まかな業界概観が必要なのか、個別具体的な企業の情報が知りたいのか、それともその企業が最近関わったニュースの分析が必要なのかなど)の目線が上位者と揃っていなければ、手戻りの原因になってしまいます。
上位者との目線合わせ、そして「そのタスクがプロジェクトにどう関係するのか(何を達成できればゴールなのか)」を常に意識することがトラブル防止の鍵かもしれません。
ジャストアイデア

ジャストアイディアですが、●●するのはどうでしょうか?
| ▼意味▼ Just Idea(ジャストアイデア)は、和製英語で「思いつき」という意味があります。海外では、”It’s just an idea…”のように、単に「アイデア」と表現されることが多いですが、日本のコンサル現場では、「ジャストアイデア」と表現されることが多い印象です。 |
コンサルはロジックを積み重ねる仕事が大半だと思われがちですが、実はアイデアをブレストする機会も多いです(特に新規事業開発などの新しいことに挑戦するプロジェクトの場合)。
ブレストする中で、ロジックが完全に整っていないという理由で発言を躊躇うのではなく、「ジャストアイデアですが…」と前置きすることで期待値を下げつつ、自分の意見を話すようにしましょう。
とにかく思いついたことを口に出していると、何か重要な発見に繋がるかもしれません。黙っているよりも口に出す方が100倍プロジェクトに貢献している、と思って筆者はいつも仕事をしています。。。(笑)
ロジ(ロジ周り)

来週、クライアントと会食があるから、諸々ロジお願いしてもいい?
| ▼意味▼ 「ロジ」または「ロジ周り」とは、「ロジスティックス」の略語で、何かを実施するために必要となってくる一連の手続きを指します。一般的には、プロジェクトの計画や実行に必要な調整や手配、準備などが含まれます。 この例文では、会食先のリサーチや予約、先方への場所連絡などを「ロジ」として表現しています。傾向として、若手がロジ回りを任されることが多いです。 なお、近い言葉として「ファシリ」が挙げられます。 |
ロジ周りを完璧にこなすのは大変ですよね。しかも、ロジを任されるのは入りたてのコンサルタントであることが多いため、入社したばかりだと特に勝手がわからず余計にストレスを抱えることが多いと思います。
ロジ周りに関してはルーティンワークなので、プロジェクトの同僚に「ロジ周りの実施内容一覧やTipsなどがまとまっていないか?」と聞いてみるのもお勧めです。長く続いているプロジェクトの場合、対応内容のメモが残っていることもありますので、試しに聞いてみてください。
インビ

明日の会議、みんなにインビ送っておいてね。
| ▼意味▼ 「Invitation」の略語となります。略さずそのままインビテーションと言う事もあります。 コロナ禍をきっかけに、TeamsやZoomなどのオンラインで会議をすることが増えましたが、会議参加者に会議用リンクを送る、という意味で使われます。 オンラインだけではなく、対面会議の場合でも、会議招集メールを送るという意味で「インビ」という言葉は使われます。 要は、インビを送る=会議招集を送る、です。じゃあ”会議招集送る”で良いのでは?と思った方もいるでしょう。まさにそうなのですが、コンサルは横文字を使いたがる人種なのです。何卒ご理解ください。 |
オンライン会議の場合、TeamsやZoomなどを使うことになると思いますが、所属しているチームやクライアントによっては、会議で使うツールが異なるケースもあります。外部の方々が利用できない場合もあるので、インビの中身には注意が必要です。
対面会議の場合は、会議室を事前に予約する必要がありますが、それがきちんとできているか、そしてインビメールを送る際に、その会議室情報が記載されているか、なども確認しておきましょう。単純なタスクほど、気をつけたいポイントです。
アジェンダ

今日の会議、資料は用意しなくていいから、最低限アジェンダだけは作ってくれない?
| ▼意味▼ シンプルに「議題」という意味です。会議を始める上で、やるべきこと・話したいことを最初に簡単にまとめたものを「アジェンダ」と言います。 つまり、議題=アジェンダ、となります。やはり横文字大好きな人種ですね。 |
コンサルは、どのような会議においても、まずアジェンダを明確に設定することが求められます。これは何故かというと、すべての会議に目的・ゴールがあり、それを達成するためのステップとしてアジェンダがあるからです。
会議のファシリテーションを任された場合、まずはアジェンダ設定(と各アジェンダで何を話し、どのような結論に導きたいか)を考えてみてください。それを意識した会話運びをシミュレーションすることで、少しずつ会議のファシリテーションができるようになっていく実感があります。
モジュール

この研修は、「ドキュメンテーション」と「ロジカルシンキング」の2つのモジュールで構成されています。
| ▼意味▼ 「モジュール」とは、一般的にはハードウェアやソフトウェアを構成する個々の部品のことを指しますが、コンサルの現場では、「カテゴリ」や「領域」という意味で用いられることも多いです。 |
コンサルの一般的なモジュールの使い方は上記の通りですが、システム関係を取り扱うプロジェクトの場合、モジュール=機能として認識されることもあり、文脈には注意が必要です。『明日は、「データドリブン経営」と「SAP」の2つのモジュールで構成された研修を行います。特に「SAP」では「FI」「MM」「SD」の3つのモジュールについて扱いますので、事前に準備をしておいてください。』と言われても、混乱しないようにしましょう。
アカウント

○○アカウントだけど、今後当社としてもっと積極的に投資すべきだと思う。
| ▼意味▼ 特定のクライアントにおいて、自社で支援している全プロジェクトやそのチームを指します。主に社内向けに使うので、クライアントにはあまり言いません。 正直、コンサルの現場での使用頻度はそこまで高くない印象ですが、参考程度にご紹介します。 |
この言葉は日常業務ではあまり使いませんが、部署や会社の全体会議で耳にすることがあるかと思います。重要アカウントとして会社から認識されているクライアントを担当する場合、とりわけ会社からの期待値は大きくなることになります。
アジャイル

このプロジェクトは、なるべくアジャイルで進めていこう。
| ▼意味▼ 「アジャイル」は、元々システム関連の言葉ですが、コンサル現場で使われる際には、「迅速さ」「素早さ」などという意味で用いられることも多いです。主に状況や仕様の変化に柔軟に対応しながらプロジェクトを進めていく状態を指します。効率的にアジャイルを回すためには、関係者同士の密なコミュニケーションが必要となってきます。 |
前述でも紹介した通り、元々システム開発発祥の言葉なので、特にシステム関連のプロジェクトで良く聞かれる言葉だと思います。プロジェクトの進め方によって、日々のスピード感や求められるものが変わってくるため、プロジェクト始めにしっかり上長と目線合わせをしておきましょう。
BPR

過去私が担当したプロジェクトはBPR系が多かったです。
| ▼意味▼ BPR(ビーピーアール)は「Business Process Re-engineering」の略語です。 日本語にすると「ビジネスプロセス再設計」ですが、つまりは、「業務改革」することを言います。既存業務や組織の在り方などを抜本的に見直し、再設計していくことを「BPR」と呼びます。 |
BPRは業務コンサルタントがよく担当しているプロジェクトスコープで、システム導入の前に行われるケースが多いと思います。現在のクライアントの業務一覧を洗い出し、業務を取捨選択した上で、新たな業務を再設計していくのが主な流れです。その他の業務コンサルタントの業務に関しては、事例を交えてこちらの記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。
BPO

クライアントA社が経理業務を外部委託したいらしいから、BPO企業の比較一覧つくってくれない?
| ▼意味▼ BPO(ビーピーオー)は「Business Process Outsourcing」の略語です。 「BPO」とは、企業の業務プロセスの一部または全部を、外部の専門業者に委託することを言います。 |
業務コンサルタントがよく手がけている内容です。近しい概念として「シェアードサービス化」(グループ企業への業務集約)もあります。事業の付随的に発生する間接費用を抑える目的で、主にバックオフィス業務(例えば給与計算や入社・退社手続きなど)を他の委託会社に外出しすることが多いです。
PMO

このシステム導入プロジェクトに、PMOとして入ってくれない?
| ▼意味▼ PMO(ピーエムオー)は「Project Management Office」の略語です。 プロジェクトを効率的・効果的に進めるために、プロジェクトにおける情報などを部門横断的に一元管理する支援機能、部門、チームのことを「PMO」と呼びます。 |
システム導入プロジェクトで置かれることの多いPMOですが、プロジェクトの遅延防止・リスク管理という意味で、何かしらの変革の実行フェーズにおいて必要不可欠な存在になってきています。
近年ではプロジェクトマネジメントの専門資格への注目が集まるなど、PMOを専門性として認識する動きも進んでいます。
PMOの業務に関しては、詳しくこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
RFP

このサービス、ホームページに掲載されている情報が粗いから、RFPを出すしかないね。
| ▼意味▼ RFP(アールエフピー)は「Request For Proposal」の略語です。 RFP=提案書や見積依頼書、となります。 |
システム導入プロジェクトで製品選定をする際にRFPを各ベンダーに出すケースもあれば、クライアントから「こういうプロジェクトをやりたいのだけど…」とRFPを受けることもあります。
コンサルの立場としてRFPを作成する場合は、As-is, To-be, 2つのギャップ、といったストーリー構築が必要になります。以前のテンプレートがないか、またサンプルがないか、など同僚や上長に確認して作業を進めることをお勧めします。
まとめ
ここまで数々のコンサル業界用語をみてきましたが、すべて分かりましたか?もし、聞き馴染みのない言葉があれば、意味を理解して、瞬時に反応できるようにしておきましょう。
その他にも、コンサル業界用語が多くあるので、ご興味のある方はこちらの用語集をご確認ください。
[v010]
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー
- 平日はコンサル、土日はアメフト選手として活動中。一流なコンサル・アメフト選手になれるよう日々奮闘中。最近の悩みは、パンプアップし過ぎてスーツが着れなくなってきていること。
著書紹介
おすすめサービス
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー
- 平日はコンサル、土日はアメフト選手として活動中。一流なコンサル・アメフト選手になれるよう日々奮闘中。最近の悩みは、パンプアップし過ぎてスーツが着れなくなってきていること。