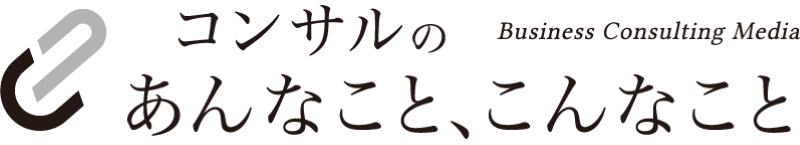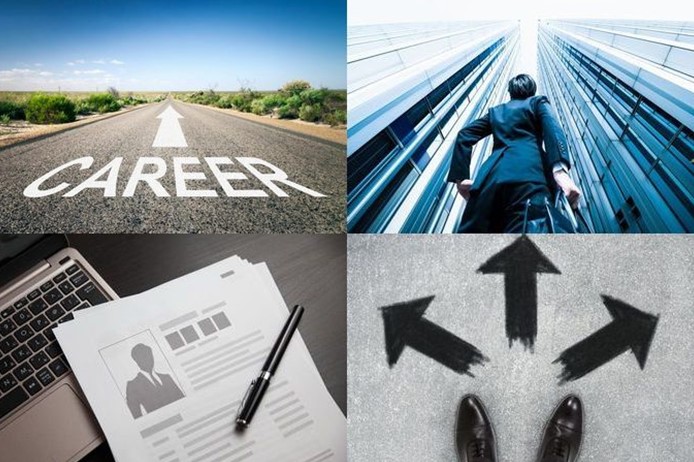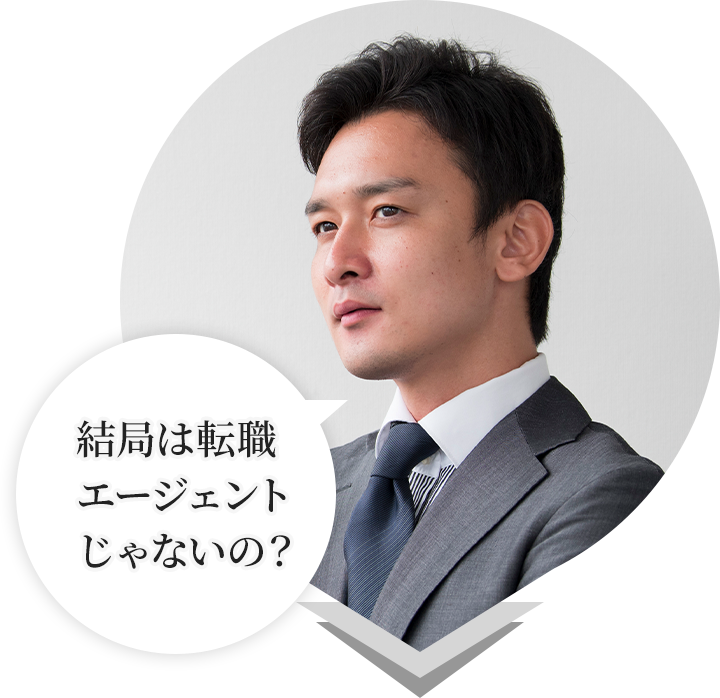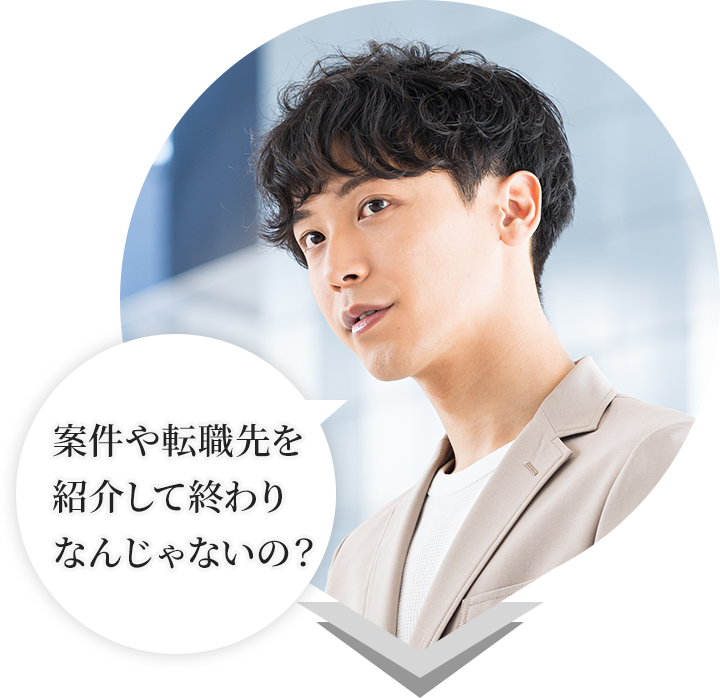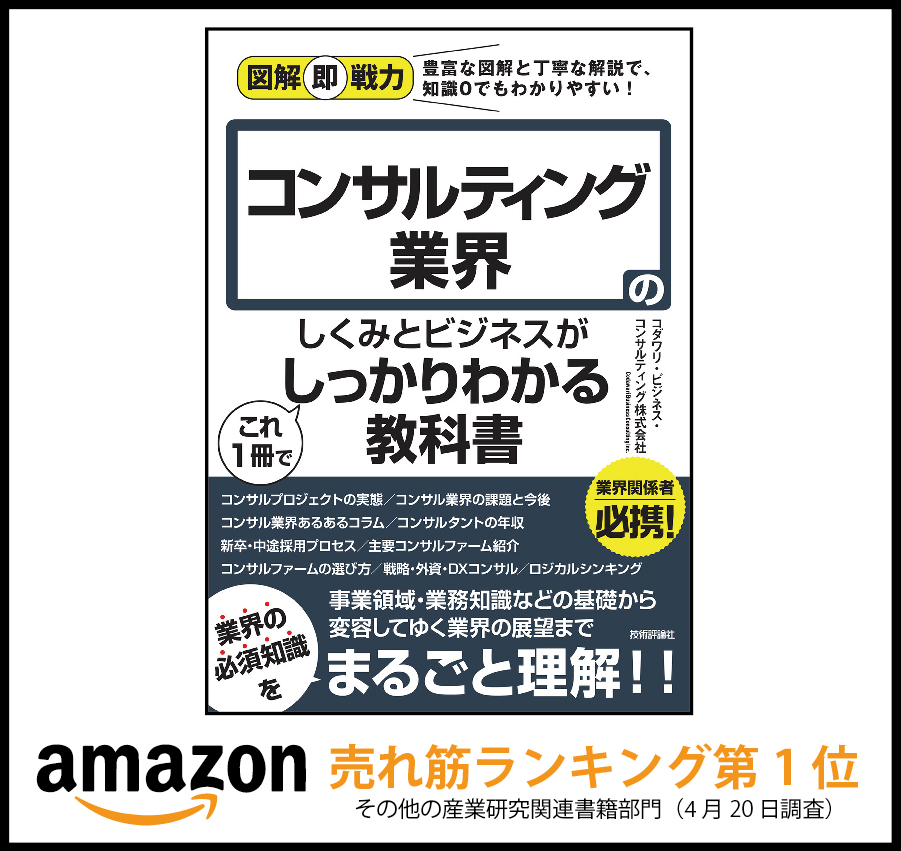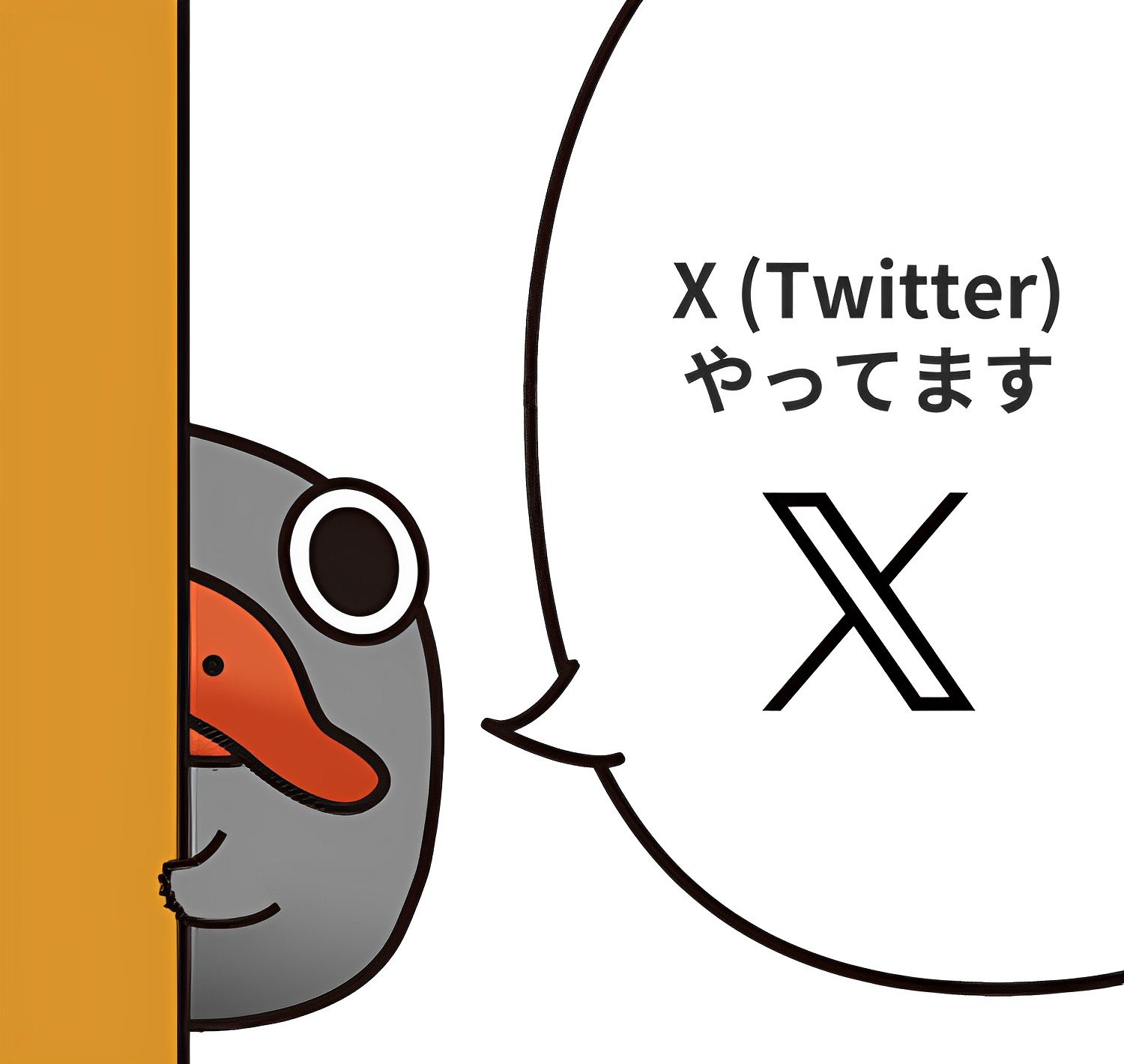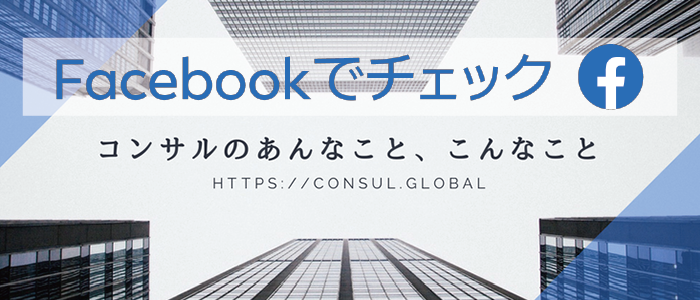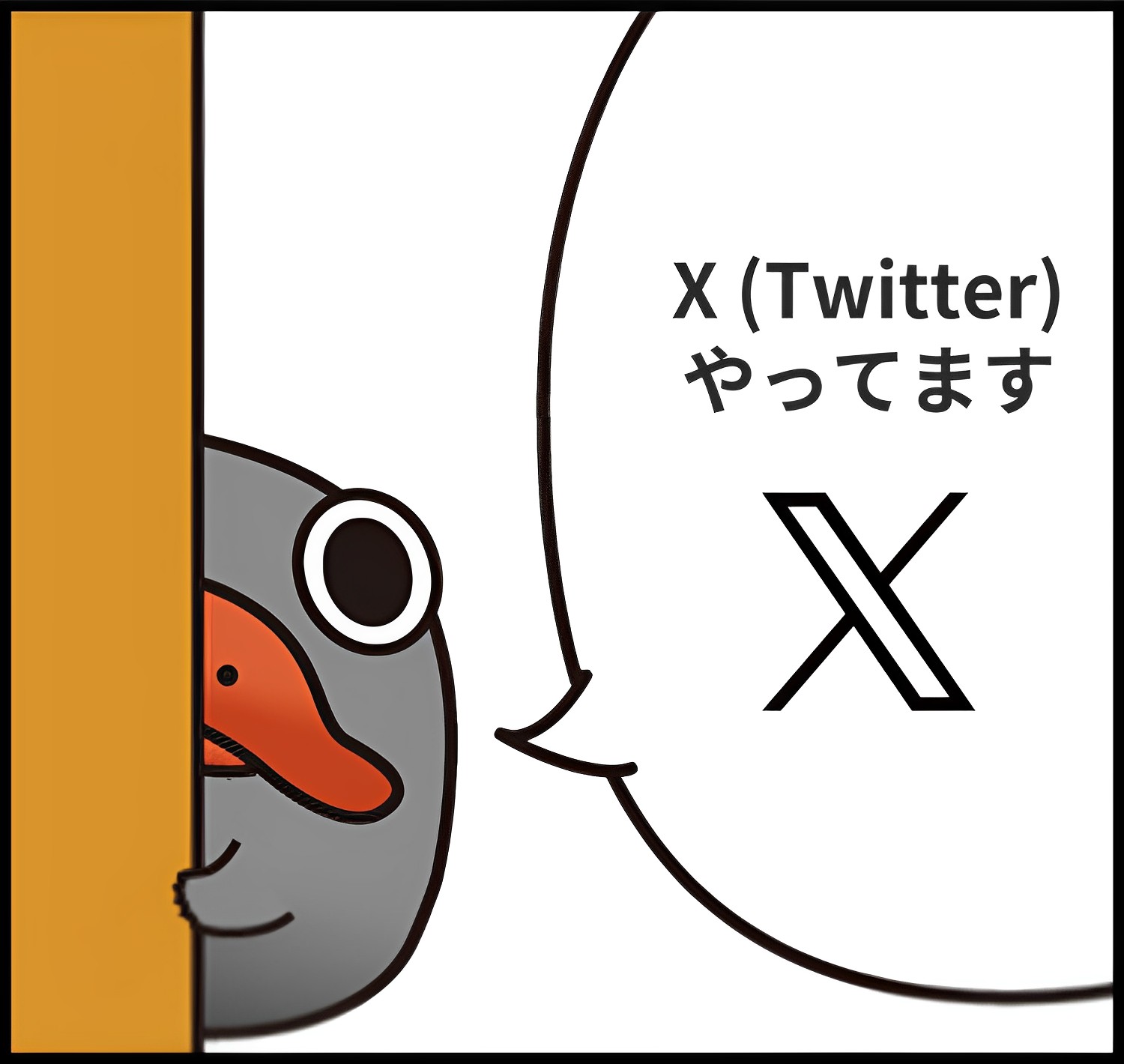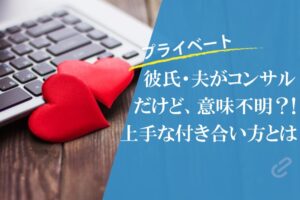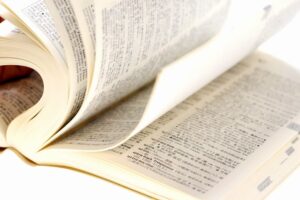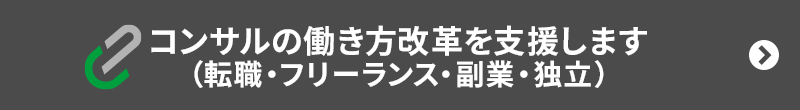view 2225
構想策定フェーズにおけるコンサルファームとシステム導入ベンダの違い

ファームとベンダのアプローチは大きく異なるため、発注側も目的を明確化することが重要
フリーコンサルの羽生です。以前、ITベンダが抱えるコンサルティングチームの一員としてクライアントのBPR構想策定プロジェクトにアサインされていたことがありました。コンサルファーム出身者の私は、これまでコンサルファームやクライアントサイドで支援することはあっても、ベンダの立場で働くことはありませんでした。それゆえか、構想策定の進め方やアウトプットに対するこだわりのようなものが、ファームのソレとは違う部分があったので、今回はこのことをざっくばらんに書いてみようと思います。
もちろん、一案件の経験を「ITベンダとは、~である」と一般化するつもりもないので、「あー、そんなこともあったのね(笑)」というお気持ちでお読み頂けると幸いです。
目次
■どんな案件だった?
クライアント名は明かせませんが、ある大手企業で、他社から受注しているBPO業務のクラウド化を行なうにあたり、働き方改革も兼ねつつ、システム化方針を検討しよう!という案件でした。当然、受注しているBPO業務がたくさんあるので、抽出してまずは10個を検討することとなりました。
カウンターは、システム部門の方が主担当で、現場の方はあまり前面に出てきませんでした。
成果物は、関係者一覧、現行業務フロー、あるべき業務フロー、システム概要図、システム化方針書、機能一覧、非機能要件、などなどで、期間は数ヶ月というタイトな計画でした。
■コンサルファームのアプローチ
ファームでしたら、まずは現行の業務/システム整理から入り、次にToBeの検討に入ると思います。少なくとも過去の案件ではそうでした。
したがって、私の進め方のイメージは、要件定義書や設計書の読み込み、現場有識者のヒアリングを通じて、現行の課題点含め整理しながらToBeの検討に入っていく流れを想定していました。成果物の因果関係もあるので、関係者一覧→業務フロー(現)→システム概要図(現)→機能一覧(現)→ToBe系の成果物、といった流れでしょうか。
———————————————————–——–——–——–
構想策定フェーズ等コンサル案件をお探しの方はこちら
———————————————————–——–——–——–
■ベンダのアプローチ
ベンダの場合は、「現在どうなっているか?」という分析に重きを置かず、「どの技術で何ができるか?」という点を重視する進め方でした。ゆえに、現行の業務整理はほどほどの品質でよく、クライアントの主担当も業務の有識者ではないシステム部門メンバということもあいまって、いきなりToBeのシステム概要図や利用する技術を説明する流れでした。BPR案件のはずなのに、業務の現/新整理もあまりせず、いきなり構築システムの青写真を描いていたということになります。
私としては、業務整理もせずに進めると、少なくともUATで現場が荒れるのでは?と思いました(今でも思っています)。
■考察:ファームとベンダが補完しあえば、クライアントはハッピーになる(かも)
ファームの強みがあればベンダの強みもあると感じました。
ベンダの強みは何といっても具体的なシステム像を提示することができるという点です。構想策定段階で具体的なテクノロジーを選び提案し、出来上がる“モノ”を説明できることは、相手を安心させることにつながると思います。
一方、弱みはシステム外の領域です。業務のFit&Gap分析や、リリースされたときの業務オペレーション、教育トレーニング、プロジェクト全体を含めたマネジメントといった領域は不得手かもしれません。
裏を返せば、コンサルファームはクライアントの真の課題感を把握し、システム導入や入れ替えありきではない方針を検討し提案、そして実行する支援に長けていますし、コンサルの真価とも言うことができます。
こういった領域をファームにカバーさせると、クライアントも少しは楽に(?)プロジェクトを進められるのではと感じます。
■クライアント目線で言えば
こうやって書いてみると結局、発注側がプロジェクトの性質を押さえて組織を検討し、役割を明確にした上でファームやベンダに発注することが大事だと思います。つまり、自社の課題感が明確である場合や目的が明確であることが大事であり、それに応じて支援発注先を選定すれば良いのです。
一方で、課題が曖昧である、どうするべきか悩ましいというのであれば、コンサルに相談するのが良いのではないかと考えます。ただ、コンサルティングファームでも自社でシステム開発を行うところが多く(特に大手ファーム)、システムありきで提案してくることが往々にしてあります(ベンダと変わらなくない?ということになります)。そういった場合には、複数のファームに相談してみる、セカンドオピニオン的に示唆を与えてくれるファームにも声をかけてみるのが良いでしょう。
当メディア運営会社、コダワリ・ビジネス・コンサルティングにも同様の相談が来ると聞いていますので、相談先の一つとして検討してみてもいいかもしれません。
お気軽にこちらまでお問い合わせください。
[v117]
執筆者
- 大手コンサルファームに複数所属後、フリーのコンサルとして独立。独立後10年以上の経験があり、無駄なコンサルをしないことにこだわっており、的を射た支援に好評がある。好きな言葉は、「守文則難」。
最新の投稿
著書紹介
おすすめサービス
執筆者
- 大手コンサルファームに複数所属後、フリーのコンサルとして独立。独立後10年以上の経験があり、無駄なコンサルをしないことにこだわっており、的を射た支援に好評がある。好きな言葉は、「守文則難」。